国民健康保険税
国民健康保険税のご案内
国民健康保険税は、当該年度の医療費の総額を推計し、病院でお支払いただく一部負担金や国からの補助金等を差し引いた額について、下記の3つの計算方法を組み合わせて税額が決まります。
| 所得割 | 世帯の所得による計算 |
|---|---|
| 均等割 | 世帯の国保加入者数による計算 |
| 平等割 | 1世帯あたりの金額 |
なお、所得の状況に応じ、税額の軽減措置を受けることができます。(世帯に前年分所得について申告していない方がいる場合は軽減措置を受けることができません。)加入者に「未就学児」がいる場合は、その方の均等割は【5割軽減】で計算します。
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となり、世帯主が国保加入者ではない場合でも、家族に国保加入者がいる場合は世帯主が納めます。
また、年齢によって保険税の計算方法が異なります。
納付方法
国民健康保険税は、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)と特別徴収(年金からの天引き)の2つの納付方法があります。
下記の特別徴収の対象となる世帯以外は、普通徴収(納付書又は口座振替)となります。
特別徴収(年金からの天引き)の対象となる世帯
1~3のすべてにあてはまる場合が特別徴収の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入していて、世帯の中で国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満の場合。
- 世帯主の1年間の年金受給額が18万円を超える場合。
- 世帯主が介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)対象者であって、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合。
納付の時期
| 普通徴収 (納付書・口座振替) |
7月(1期)~2月(8期) 年税額を8期で割った額 その他資格に異動があった場合は、3月(随1期)・翌年度4月(随2期)に納付いただく場合があります。 |
|---|---|
| 特別徴収 (年金からの天引き) |
仮徴収:4・6・8月(1~3期) 前年度の国民健康保険税を年金の支払回数(年6回)で割った額(翌年度からは前年度6期の額) 本徴収:10・12・2月(4~6期) 年税額から仮徴収した税額を差し引いた残額 満75歳になる年度は、普通徴収になります。 |
税率
国民健康保険税の計算方法(令和7年度)
国民健康保険税の計算方法は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護保険給付分について下記のように計算して合計します。
- 所得割課税標準額=前年の所得金額-43万円(基礎控除) ・・・A
医療給付費分
| 所得割額 1 (被保険者ごとに計算し合計する) |
A×7.85% |
|---|---|
| 均等割額 2 | 25,600円×世帯の被保険者数 |
| 平等割額 3 | 1世帯あたり 18,400円 |
| 医療給付費分 合計 | 1+2+3=X (賦課限度額 660,000円) |
後期高齢者支援金分
| 所得割額 4 (被保険者ごとに計算し合計する) |
A×2.59% |
|---|---|
| 均等割額 5 | 8,400円 ×世帯の被保険者数 |
| 平等割額 6 | 1世帯あたり 6,000円 |
| 後期高齢者支援金分 合計 | 4+5+6=Y(賦課限度額260,000円) |
介護保険給付費分 40歳以上65歳未満の被保険者が該当
| 所得割額 7 (被保険者ごとに計算し合計する) |
A×1.96% |
|---|---|
| 均等割額 8 | 8,400円 ×世帯の被保険者数 |
| 平等割額 9 | 1世帯あたり 3,800円 |
| 介護保険給付費分 合計 | 7+8+9=Z(賦課限度額170,000円) |
1年間の国民健康保険税額=X+Y+Z
軽減等について
低所得世帯に対する軽減
世帯の軽減判定所得が、下記に該当する場合は、保険税の均等割と平等割が軽減されます。
※申請の必要はありませんが、世帯主および被保険者が前年中の所得を申告している場合に限ります。
| 軽減割合 | 世帯主および被保険者等の軽減判定(前年所得) |
| 7割 |
基礎控除額(43万円) +10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割 |
基礎控除額(43万円)+30万5千円×(被保険者数) +10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割 |
基礎控除額(43万円)+56万円×(被保険者数) +10万円 × (給与所得者等の数-1)以下 |
●軽減判定所得について
軽減判定所得金額は、下記により算出します。
| (1) 前年中の総所得金額等(※1) | ⇒ |
(1)+(2)+(3) 軽減判定所得金額 |
| (2) 専従者給与(控除)額(※2) | ||
| (3) 軽減判定上の純損失繰越控除額(※3) |
(※1)
- 総所得金額および山林所得ならびに分離課税所得の合計額です。退職所得は含みません。
- 総合課税分の長期譲渡所得および一時所得は、2分の1の金額で、土地・建物等の分離課税の譲渡所得は、特別控除適用前の金額で判定します。
- 65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
(※2)
- 事業主は青色専従者給与額、事業専従者控除を必要経費とせず判定します。また、専従者が事業主から支払いを受けた給与(専従者給与)は軽減判定所得には含みません。
(※3)
- 軽減判定上の純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。
産前産後期間の軽減
国民健康保険の被保険者が出産された際、出産された被保険者にかかる国民健康保険税が届出(申請)により一定期間軽減されます。詳しくは下記のチラシをご参照ください。
非自発的失業の軽減
非自発的失業(倒産・解雇・雇止めなどによる離職)により、国民健康保険に加入した方については、国民健康保険税や高額療養費等の自己負担限度額が軽減される制度があります。
軽減を受けるためには申請が必要です。他市区町村で軽減を受けていた方が転入してきた場合にも、改めて申請が必要となります。
詳しくは、下記のチラシをご参照ください。
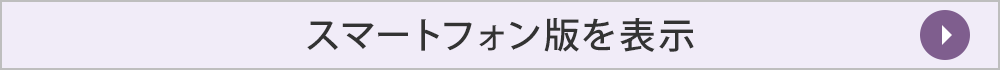






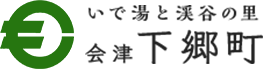
更新日:2025年06月20日